目次
中期経営計画「5カ年ローリングプラン2019」
オートバックスと経営理念
「最適なカーライフの提案」と「豊かで健全な車社会の創造」を経営理念とするカー用品販売再大手・オートバックスセブン。売上:2,000億円超、営業利益:75億円超、時価総額:1,500億円と日本を代表する大企業です。
オートバックスの事業内容、決算情報、時価総額などは
【最新決算&メカニック視点】オートバックス大解剖!
車のアフターマーケット関連企業と言われて、真っ先に思い浮かぶ会社「AUTOBACS(オートバックス)」。大阪にて自動車部品の個人商店(卸売)から始まった株式会社オートバックスセブン。カー用品の小売やFCにて業容を拡大し東証一部に上々する大企業です。近年では、車検を中心に整備・アフターサービス事業も拡大し、僕たち整備士にとっても身近な会社になってきました。そんなオートバックスを、最新決算(2020年3月期)をもとに、メカニックの視点で分析します。
https://seibii.co.jp/blog/contents/autobacks-analysis/
5カ年ローリングプラン2019
2019年4月以降の5年間で取り組んでいく方向性として「5カ年ローリングプラン2019」を発表しています。中身の詳細は公表されていないのですが、以下の「6つのネットワーク」を「確立」し「連携」させることを骨子としています。
6つのネットワーク
- オートバックスチェーン
- 海外におけるアライアンス
- マルチディーラー
- 最適なサービスを提供するピット
- 次世代技術に対応する整備
- お客様とのリレーションを高めるオンライン
独断と偏見で評価
6つのネットワークーのうち「2.海外におけるアライアンス」「3.マルチディーラー」の2つのネットワークに関しては、先行きが厳しいと言わざると得ないでしょう。一方で、「1.オートバックスチェーン」「4.最適なサービスを提供するピット」「5. 次世代技術に対応する整備」「6. お客様とのリレーションを高めるオンライン」の4つのネットワークに関しては、オートバックスが既に持つ強み、マクロトレンドの双方の観点で理にかなっており、期待が持てます。
同社の経営計画は、整備事業者やカー用品事業者含め、多くの車のアフターマーケット事業者にとって参考になるでしょう。解説していきます!
赤字3事業「海外事業」「ネット・オンライン(EC)事業」「ディーラー事業」
2020年3月期、2019年3月期の2期分の決算のみから判断するに、「海外事業」「ネット(EC)事業」「ディーラー事業」の3つは、売上貢献が乏しく、赤字。テコ入れが必要な事業分野です。
海外事業
全6カ国にて、35店舗をネットワーク内に有し、toC(小売)とtoB(卸売)を行っています。しかし、決算からは苦戦が見て取れます。
- 売上:国内オートバックスチェーン事業(店舗事業)の売上が1,800億円近くに対して、海外事業は100億程度。
- 利益:公表されている同事業部門のセグメント利益は赤字(2019年3月期:▲7.8億円、2020年3月期:▲3.6億円)
オートバックス関連海外子会社の連結営業利益に絞ると2020年3月期に29百万円の黒字を達成していますが、会社全体の規模からすると、貢献度は無いに等しいと言えます。
ネット事業とディーラー事業
オートバックスのIRではネット事業とディーラー事業が合算で説明がされています。オートバックスはBMW/MINIの正規ディーラー事業を営んでいます。これは通常の正規ディーラー事業です。ネット事業は、カー用品のECが中心となる事業です。両事業が全く異なる分野であることは明白です。これら1つのセグメントとして纏めているのは、現状の数字が小さく、決算面でも貢献が乏しいことが理由と考えられます。
赤字の「海外事業」「ディーラー事業」は先行き不明
海外事業とディーラー事業は既に存在するネットワークです。これらを、他の4つのネットワークと連携させることを中期経営計画では掲げていますが、言うは易し。参考になりそうな他社の成功事例はありません。具体的な成長戦略・勝ち筋が見えず、良く分からない、と言えそうです。
テコ入れすれば未来がある!EC・オンライン事業
「海外事業」「ディーラー事業」と異なり、やり方次第で中核事業に育つポテンシャルを有する事業が「EC・オンライン事業」です。大きなトレンドとしてジワリジワリと進んでいた「オンラン・EC化率上昇」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」「OMO(オンラインとオフラインの融合)」の波に、新型コロナ(COVID-19)が大きく後押しをしています。
リアル店舗隣接のピットネットワークが強み
シンプルなカー用品のECであれば、Amazonや楽天などの巨人に勝てる見込みは無いと言えます。ブランド力があ無印良品や多くのアパレルメーカーが、長年トライ&エラーを続けてきた自社ECを軌道に載せることができず、大手プラットフォームECに乗り越えたことからも明らかです。
しかし、車のアフターパーツ・カー用品には他商材とは異なる特性があります。それは「売って終わり」では無く、「取り付け・設備での作業」が付随することです。例えば、タイヤのゴムだけネットで買っても、タイヤ交換することは不可能です。全国600店弱の店舗ネットワークを有するオートバックスが、OMOの文脈で強みを発揮できる分野です。
期待のOMO戦略! タイヤEC事業で三菱商事グループと合弁事業開始
2020年4月、カーフロンティア社 (大手総合商社・三菱商事グループ)が展開する「タイヤのEC販売事業TIREHOOD」にオートバックスセブンが出資することが発表されました。出資比率は開示されていませんが、新会社の代表取締役はカーフロンティア社から出ていることを考えると、カーフロンティア社が50%以上の比率を持っているものと想定されます。
『TIREHOOD』は3年前から展開するタイヤのECです。三菱商事グループのガソリンスタンドを中心に、全国4,000以上の取付店舗網を有しています。
巨大市場であるタイヤ
タイヤはカー用品・パーツの中でも最も巨大な市場です。小売だけで国内5,000億円弱の市場があります。車の高度化がどれだけ進んでも、需要は無くなりません。消耗品で、夏と冬の交換需要もあります。各社TVCMを常に流しています。
オンラインとオフラインの融合が必須のタイヤ事業
タイヤ交換には設備が必須で、一般の方には手出しできません。まさに、OMOが必須の商材です。Tirehoodでは、購入から取付予約までをネット上で完結でき、UIも今風で使い易いやすいWebサービスです。ここに、タイヤ販売の売上比率が高く、全国に交換設備を有する店舗・ピットネットとワークを有するオートバックスが出資することは理に適っているいると言えます。
実態は苦しい? Tirehood事業
大きな可能性が期待できる一方で、TIREHOOD事業は苦戦していたであろうことが想像できます。単独での売上や利益は開示されていませんが、カーフロンティア社の決算公告を見ると、2018年:3億5千万円の赤字、2019年:7億4千万円の赤字と会社業績は乏しくありません。カーフロンティアは車のアフター関連事業を7つ運営しており、個別の収益は開示されていません。しかし、Tirehood事業が利益を生み出しており、今後も順調な成長が期待されてるのであれば、虎の子の運営権を手放すことはしないでしょう。
「ポテンシャルはあるが、単独での運営では実効性が乏しかった」が実態と想像できます。
本丸!次世代技術に対応する整備ネットワーク構築
タイヤEC・OMO事業以上に大きな期待が持てる戦略、それが「次世代整備ネットワーク構築」です。具体的には3つの手を打っています。
- 整備工場の買収
- 既存整備事業者団体との提携
- テスラとの取り組み
詳細を解説していきます!
整備事業の大きな変化「特定整備」
車の高度化に合わせて、「特定整備」と呼ばれる新制度が2020年4月から施行されました。詳しくは
特定整備 - 内容と事業者への影響
「特定整備制度」が2019年5月に公布、2020年4月に施行されました。これにより、分解整備の【範囲が拡大】し【対象装置の追加】がなされ、その名称を「特定整備」と改めることとなりました。「特定整備」の許可を得た事業者のみ、特定整備で定義される作業を実施することができます。この点は従来の分解整備と変わりません。この特定整備制度、消費者はもとより、自動車整備業を営む方々や自動車整備士に大きな変化を及ぼします。その一方で、新制度への過渡期でもあり、特定整備に関する情報が理解し難いところがあります。そこで、特定整備に関する内容、背景、私たち事業者への影響を纏めました。
https://seibii.co.jp/blog/contents/tokutei-seibi/
打ち手1. 衝撃の自動車整備工場買収
整備関係者にとって衝撃のオートバックスによる街の整備工場買収。これまでに2件完全買収しています。これらは、特定整備への変革に沿った打ち手です。
- 滋賀県栗東市:正和自動車販売株式会社
- 三重県津市 高森自動車整備工業株式会社
既に店舗・ピット網を有するオートバックスが独立系整備工場を買収する理由
オートバックスは約600店舗ネットワークを通じて整備・ピットサービスを既に提供しています。それでも街の整備工場の買収に踏み切った理由として以下の通り考えられます。双方にとってメリットがあると言えそうです。
街の整備工場視点でのメリット
- 全国5万6,000以上存在する街の整備工場(専業整備事業者)は過当競争に晒されており、生き残り戦略が必須
- 街の整備工場単独では、特定整備に対する「投資」と「回収(セールスとマーケティング)」に限界がある
オートバックス視点でのメリット
- 約600店のうち、直営店は20店舗のみで、ほとんどがフランチャイズ(FC)
- フランチャイズ店舗は本体からのコントロールが効き難い
- 店舗数は競合対比十分とは言えない(競合のイエローハットは全国738店舗)
打ち手2. 整備事業者団体「BSサミット」との提携
2020年8月、オートバックスと、独立系整備・修理事業者345社が加盟するBSサミット事業協同組合は、特定整備を含む、次世代技術への対応を見据えた「包括的業務提携」を締結したと発表しました。具体的には、以下3つの狙いがあります。
- 600店舗を有するオートバックスと、345社・500拠点を有するBSサミットの、各々の拠点地域を合算することで、対応可能地域を増やす
- 各々が対応できるサービス(軽整備、重整備、板金・塗装、ロードサービス)を合算することで、対顧客向けにワンストップを実現する
- 特定整備に対応する人材、特定整備専用の設備の相互補完・活用
特定整備に必要な認証を取得するには、作業場や整備機器、整備士資格などが必要です。一方で、人材確保・資金面で、整備事業者にとっては負担が大きいのが実態です。また、過当競争による集客合戦も事業者単体にとっては悩みの種となっています。この点を総合に補完する狙いがあるようです。
この提携により「オートバックス」にとっては、受け入れ能力・対応メニューの向上により、固定客の流出防止を図るメリット、「BSサミット」にとってはオートバックスセブンの集客力を生かした入庫拡大が期待できるメリットがあります。
打ち手3. 次世代自動車への布石:テスラとの提携
オートバックス旗艦店「A PIT AUTOBACS SHINONOME」に電気自動車メーカー最大手・テスラのサービス拠点が入居しました。「間貸し」をしているだけと言えばそれまでです。
しかしテスラの事業展開方針は以下の通りとなっています。
- ディーラー網を整備せずにECで車を販売していく方針
- 整備・修理は出張整備カーが出動して対応
こう考えると、非正規ディーラーで全国に店舗・ピット網を有するオートバックスのネットワークを、テスラが将来活用する絵は自然とも言えます。数年先の話かもしれませんが、テスラxオートバックスの整備ネットワーク、期待が持てそうです。
参考URLリスト
本記事では以下Webサイトを参考に記載しました。
株式会社オートバックスセブンIR・ニュースリリース
- 「5 ヵ年ローリングプラン 2019」の策定に関するお知らせ(2019.05.08)
- 2020年3月期 決算説明資料(2020.05.22)
- 高森自動車整備工業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ (2020.02.28)
- 正和自動車販売株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ(2019.05.07)
- A PIT AUTOBACS SHINONOME敷地内に、新テナントが出店
「テスラ サービスセンター東京ベイ」オープン(2019.05.10)
株式会社カーフロンティア・ニュースリリース
官報決算データベース
その他
- イエローハットHP
-
特定整備 - 内容と事業者への影響
「特定整備制度」が2019年5月に公布、2020年4月に施行されました。これにより、分解整備の【範囲が拡大】し【対象装置の追加】がなされ、その名称を「特定整備」と改めることとなりました。「特定整備」の許可を得た事業者のみ、特定整備で定義される作業を実施することができます。この点は従来の分解整備と変わりません。この特定整備制度、消費者はもとより、自動車整備業を営む方々や自動車整備士に大きな変化を及ぼします。その一方で、新制度への過渡期でもあり、特定整備に関する情報が理解し難いところがあります。そこで、特定整備に関する内容、背景、私たち事業者への影響を纏めました。
https://seibii.co.jp/blog/contents/tokutei-seibi/
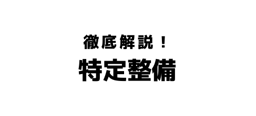
-
【最新決算&メカニック視点】オートバックス大解剖!
車のアフターマーケット関連企業と言われて、真っ先に思い浮かぶ会社「AUTOBACS(オートバックス)」。大阪にて自動車部品の個人商店(卸売)から始まった株式会社オートバックスセブン。カー用品の小売やFCにて業容を拡大し東証一部に上々する大企業です。近年では、車検を中心に整備・アフターサービス事業も拡大し、僕たち整備士にとっても身近な会社になってきました。そんなオートバックスを、最新決算(2020年3月期)をもとに、メカニックの視点で分析します。
https://seibii.co.jp/blog/contents/autobacks-analysis/

-
自動車整備業界の基本 - 工場数と従事者(2023年最新版)
自動車整備業界は、9万1,711もの工場、54万7,332人もの人たちが働いている大きく重要な産業です。自動車整備業界について理解しようと思うと、2020年4月に施行された特定整備(分解整備、電子制御装置整備)、指定工場(民間車検場)、認定工場など、日常生活では馴染みの薄い単語を理解する必要が出てきます。この記事では、最新統計(2022年)の工場数、従事者数、整備士平均年齢の観点から自動車整備産業の外観を整理していきます。
https://seibii.co.jp/blog/contents/car_maintenance_industry_overview/











